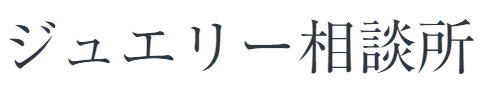※本ページではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています※
ピアスの穴が開いていなくても子供から大人まで着けられて人気のジュエリーであるイヤリング。
しかし、着けていると耳が痛くなってしまうことがよくあります。
じんじんとしたあの痛み無しでイヤリングを楽しみたいですよね。
そこで今回は、イヤリングの基礎知識と、イヤリングを着けた時に生じる痛みの対処法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
それではご覧ください!
1.イヤリングで耳が痛くなってしまう3つの原因

そもそも、イヤリングを着けているとどうして耳が痛くなってしまうのでしょうか。
その原因は大きく分けて3つあります。
まずは、どのような原因で耳が痛くなってしまっているのか知りましょう。
1-1.挟む力が強すぎる

イヤリングは、留め具で耳たぶを挟むことで固定されています。
この挟む力が強すぎると、痛みが生じてしまいます。
挟む強さを調整できない留め具も多いため、このような事態が起きてしまうのです。
また、挟む強さを調整できる留め具の場合でも、イヤリングを失くしてしまうことを危惧して必要以上にきつく締めてしまい、それが原因で痛みが生じてしまうこともあります。
1-2.長時間の着用で血流が悪くなった

留め具の強さは丁度良かったとしても、イヤリングを長時間着け続けると耳たぶに圧力がかかり続けるため、痛くなってしまうことがあります。
きついカチューシャを着けているとこめかみが痛くなってくるのと同じで、耳たぶを挟むことによって血流が阻害されたり神経を刺激したりしてしまうのです。
1-3.1ヵ所に圧力が集中している
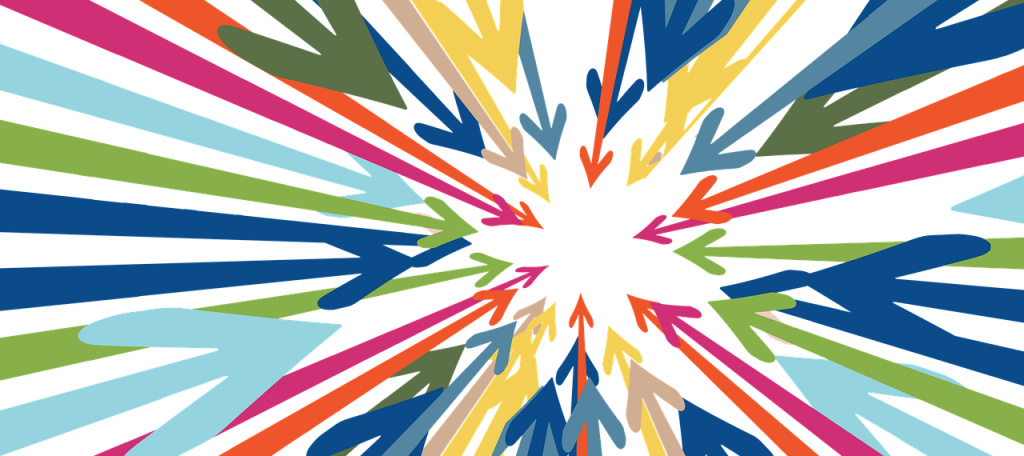
留め具が細く華奢なものであると、留め具と耳たぶとの接地面が少なくなります。
その分1ヵ所にかかる圧力が大きくなり、痛みが生じてしまうということもあります。
2.イヤリングの留め具の種類

このように、イヤリングを着けていて耳が痛くなってしまうのは、耳たぶを挟む留め具の部分で問題が起こっている場合が多いのです。
では次に、その留め具の種類について見ていきましょう。
留め具の種類によって、その特徴や痛みが生じやすい理由は異なります。
耳が痛くなってしまった時の対処法を知る前に、お手持ちのイヤリングの留め具がどの種類なのか、その留め具はどのような痛みが生じやすいのかについて見てみましょう。
2-1.ネジ式(スクリュー式)

耳たぶの裏側からネジを締めて耳たぶを挟むタイプの留め具です。
耳たぶの厚さに合わせて挟む力を調整できるため、比較的耳が痛くなりにくいです。
しかし、留め具と耳たぶの接地面が狭く一点に圧力がかかりやすいため、痛みを感じやすくなってしまうのがデメリットです。
また、痛いからと言ってあまりにも挟む力を弱くしてしまうとイヤリングを紛失してしまう可能性もあるため、丁度良い締め具合を探る必要があります。
2-2.クリップ式(バネクリップ式)

パチッと挟むだけで簡単に着脱できるクリップ式の留め具で、「着けている感」がある分、落としてしまった時などに気づきやすいです。
耳たぶをしっかりと挟み込めて安定感があるため、大ぶりで重さがあるイヤリングでも着けることができます。
面と面で耳たぶを挟むため、留め具と耳たぶとの接地面が大きくなり、比較的痛くなりにくいです。
最近ではシリコン素材の緩衝材を付けて耳たぶとの接地面を通常よりも大きくしたソフトタッチクリップ式と呼ばれるものもあり、より痛みを軽減することができます。
しかし、クリップ式は挟む力を調整することができないため、人によってきつく感じたりゆるく感じたりする場合があります。
また、使っている内にバネが故障してしまうことが多いです。
2-3.ネジバネ式

ネジ式とクリップ式を組み合わせたタイプの留め具で、近頃では最も一般的に使われている留め具です。
ネジ式の留め具がクリップ式のように開閉できる造りになっており、耳たぶを挟んでからネジで締め具合を調整することができ、耳たぶの厚さに関係なく着けることができます。
しっかりと固定できて落ちにくいため、大ぶりのイヤリングにも対応できます。
しかし、ネジ式と同様に留め具と耳たぶの接地面が小さく一点に圧力がかかりやすいため、痛みを感じやすいです。
また、留め具が目立つため、見た目をすっきりさせたいという方は別のタイプの留め具を選んだ方が良いでしょう。
2-4.マグネット式

磁石の力で耳たぶを表と裏から挟んで固定するタイプの留め具です。
パチッとワンタッチで装着することができます。
留め具が目立たないため、ピアスのように見せたいという方にはおすすめです。
より本物のピアスに似せるために、裏側にピアスのポスト(軸)が突き出ているようなデザインのものも販売されています。
磁力の強さは調整できないため、強すぎたり弱すぎたりすると扱いにくい場合もあります。
2-5.パイプ式(フープ式)

フープピアスのような見た目の留め具です。
フープの一部が伸縮バネになっているため、そのバネを開いて隙間を作った後、耳たぶに差し込みます。
あとは指を離して留め具を耳たぶにフィットさせるだけで、イヤリングを着けることができます。
バネの強さを調整することができないため着け心地に個人差が出やすい、耳たぶとの接地面が少ない分一点に圧力がかりやすいなどのデメリットもありますが、フープタイプのイヤリングを着けたいという方にはおすすめです。
2-6.ソフトクリップ式

クリップ式でありながら挟む力を調整することができる留め具です。
親指と人差し指で留め具つまんで、お好みのきつさに調整してください。
徐々に締め具合を調整することができますが、その分イヤリングの紛失を恐れて強く締めてしまいがちですので、痛みが出ないように調整しましょう。
3.耳が痛くなってしまった時の7つの対処法
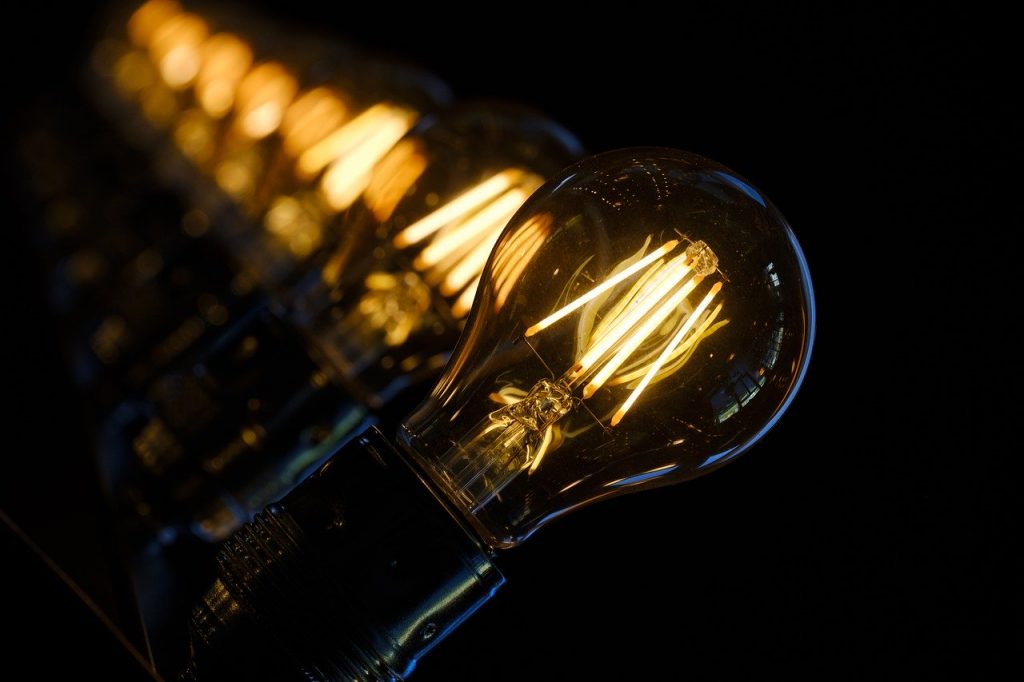
お手持ちのイヤリングに使われている留め具の種類、またその留め具はどのような痛みが生じやすいのかについてお分かりいただけたかと思います。
次に、イヤリングを着けていて耳が痛くなってしまった時の具体的な対処法についてご紹介します。
今すぐ簡単に試していただける方法も多くありますので、ぜひ参考になさってください。
①着ける位置を調整する

イヤリングを着けていて耳が痛くなってしまった時は、イヤリングを着けている位置を調整してみましょう。
イヤリングを着けていて耳が痛くなってしまうのは、そもそも痛みを感じやすい位置にイヤリングを着けてしまっている可能性があります。
イヤリングは耳たぶの真ん中につけるのが一般的ですが、より頬に近い位置に着けることで痛みを軽減できることもあります。
真ん中に着けるとイヤリング自体に動きが出てきれいに見えますが、揺れやすく不安定になり、耳でイヤリングの重みを感じやすくなります。
イヤリングを頬に近い位置に着けてこの揺れを軽減することで、痛みも軽減させることができます。
痛みを感じる場所には個人差があるため、耳たぶを指でつまむなどして痛みを感じにくい場所を探してみるのが良いでしょう。
②こまめに位置をずらす

これは、イヤリングを長時間着け続けていることによって痛みが生じてしまっている場合に有効な方法で、耳の同じ位置に圧力がかかり続けることを防止します。
イヤリングの位置を、頬寄り、真ん中、外側寄りなどにこまめにずらしましょう。
痛みを感じてからではなく、痛みが生じる前にずらすのがポイントです。
③シリコンカバーを付ける
![]()
留め具にシリコン製のカバーを付ける方法です。
特に、留め具と耳たぶの接地面が少なく、圧力が一点に集中してしまっている場合に効果的な方法です。
留め具と耳の接地面が大きくなることで圧力が分散され、痛みが生じにくくなります。
また、留め具が直接耳たぶに食い込んでしまうのを防ぐことにも繋がります。
シリコンカバーは安いものであれば100円台で購入することができるため、気軽に試していただけます。
使い方もかぶせるだけ、差し込むだけなど、簡単なものばかりです。
どのタイプの留め具にも専用のカバーが販売されていますので、ぜひお試しください。
また、もともとカバーが付属しているイヤリングも販売されていますので、新たにイヤリングをご購入される際にはそちらもおすすめです。
④両面テープを張る

こちらは、耳たぶを挟む力を調整できるタイプの留め具に使っていただける方法です。
留め具と耳たぶが接する部分に、目立たない大きさに切った両面テープを貼るだけです。
外す時は皮膚を傷つけないよう、ゆっくり剥がすようにしましょう。
※使用するテープは医療用など皮膚に貼っても大丈夫なものを使用しましょう。
また、事前にパッチテストなどを実施して皮膚に、異常が出ないかを確認してから試すようにしましょう。
⑤アイプチで固定

こちらも、耳たぶを挟む力を調整できるタイプの留め具の場合に使っていただける方法です。
アイプチは、目を二重にするための粘着力のある液体の化粧品です。
これを留め具に塗ることで、留め具の力が補強され、結果として挟む力を緩めることができます。
また、それと同時にイヤリングのズレを防止することにも繋がります。
アイプチはつけまつげのりでも代用可能で、どちらも100円均一や薬局で購入することができます。
もともと皮膚に塗るためのものであるため肌への負担も少なく、乾くと透明になって目立ちません。
また、水やぬるま湯で落とせるものも多く、後処理もらくちんで便利です。
外したイヤリングは、アイプチをしっかりと落としてから保管するようにしましょう。
※パッチテストなどを行い、皮膚がかぶれないか確認してから試すようにしましょう。
また、金属に影響が出る場合もあるため、自己責任でお試しください。
⑥挟む力を調整する

留め具の挟む力が強すぎる場合には、ご自身で調整を行うのも一つの方法です。
先が細いペンチで、留め具のネジやバネの角度や幅を調整してみましょう。
この時、大きく動かしすぎると折れてしまうこともありますので注意が必要です。
また、留め具を曲げすぎた場合に元通りに戻すことが難しいこともあるため、少しずつ調整するようにしてください。
自分で調整するのが難しい場合や壊れてしまっては困るイヤリングの場合は、ジュエリーショップなどに持ち込むのも良いでしょう。
⑦留め具の種類を変える

思い切って留め具を付け替えてしまうという方法もあります。
これは、どのような原因によって痛みが生じている場合にも有効な方法です。
近年ではハンドメイドアクセサリーが流行していることもあり、イヤリングのパーツなども簡単に購入することができるようになっています。
種類も豊富ですので、お好きな留め具に変えてみてはいかがでしょうか。
4.それでも耳が痛い方へのおすすめアイテム

対処法を試してみたけれど思ったような効果が得られなかったという方、まだ諦めないでください!
最後に「痛みを我慢してイヤリングを着けるのは嫌だけれど、耳元のおしゃれは楽しみたい!」という方向けのおすすめアイテムをまとめてみました。
ぜひチェックしてみてくださいね!
4-1.ノンホールピアス


近年、目にすることが多くなったノンホールピアス。
ノンホールピアスの多くはオメガ型の留め具が付いており、耳たぶに下から差し込むようにして装着します。
留め具が目立たないため、本物のピアスのように見えるのも人気の理由です。
また、留め具は左右対称の場合が多く、デザインによっては裏表をかえてリバーシブルで着けることができます。
一般的なイヤリングと比較して全体的に軽量で重さが無い分、耳たぶが痛くなりにくいです。
素材も樹脂を使用している場合が多く、金属アレルギーの方でも安心して使えるものもあります。
しかし、下から差し込むという装着方法の関係で、あまり大ぶりのデザインには対応できません。
耳たぶが厚い方は着けにくい場合もあったり、紛失しても気づきにくいというデメリットもあります。
また、何度も開閉を繰り返していると留め具が緩くなってきてしまうため、使い続けたい場合は留め具の交換をする必要が出てきます。
従来のものよりも耳たぶとの接地面が広く、バネのクッション性も向上した「ループフィット」と呼ばれるタイプのノンホールピアスも販売されていますので、気になった方はぜひ一度チェックしてみてくださいね。
4-2.ピアリング


ピアリングは特許を取得した技術で作られており、通常のイヤリングよりも落ちにくく、どんな耳にフィットします。
耳を挟む部分が平面になっており、痛みが生じにくいです。
また、締め具合も調整できるものもあります。
見た目もすっきりとしており、ピアスのように見えるのが特徴です。。
シルバーとゴールドなど、半分ずつで異なる色を組み合わせているデザインもあり、リバーシブルで使えるものもあります。
また、ピアリングに通して使うチャームも販売されており、ご自身でデザインをアレンジして着用することもできます。
実用性とデザイン性を兼ね備えたピアリング、試してみてください。
※正規品のピアリングには「P」のマークが入っています。
 |
ピアリング 正規品 K18 イヤリング con moto コンビ ピアリング社 リバーシブル イヤーカフ イヤークリップ ノンホールピアス コンモート 価格:18,150円 |
![]()
4-3.イヤーカフ


痛みを伴わずに耳元のおしゃれを楽しみたいという方には非常におすすめなイヤーカフ。
耳たぶを挟むのではなく軟骨部分(耳たぶ以外の部分)に引っかけるようなイメージで着用します。
装着中の痛みはほとんどありません。
大きさやデザインも様々で、個性的なものも多いです。
4-4.イヤーフック


こちらも耳たぶを留め具で挟むことはせず、耳の後ろから引っかけて装着します。
耳への負担が少ないだけでなく落ちにくいため、紛失の心配は少ないです。
大ぶりなデザインのものが多く、簡単に耳元を華やかに見せることができます。
しかし、眼鏡をかけている方は着用しにくい場合もあるようですので、注意してください。
4-5.貼るピアス
近年では、医療用シールを使用した貼るピアスが100円均一や通販サイトなどで販売されています。
貼って着用するため着けている時の痛みはなく、一日着けていても自然に剥がれてくることはありません。
また、医療用のシールを使用しているため、アレルギー反応などが起こる心配がありません。
小ぶりなデザインのものだけでなく長さのあるデザインのものなどもあり、ご自身のファッションや気分に合わせて気軽に楽しんでいただけます。
シールの粘着力が落ちたら、新しいシールに張り替えれば繰り返し使うことができます。
終わりに
いかがだったでしょうか。
この記事を読んで、イヤリングを着けた時の痛みが少しでも解消できていたら幸いです。
ジュエリーに関するお悩みがございましたら、下のコメント欄、メール、Twitterからお気軽にお送りください。
またジュエリー相談所では、ジュエリーや宝石の販売も行っております。
「ジュエリーや宝石に興味が湧いた!」という方は、ぜひこちらもご覧ください。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。